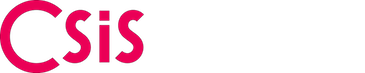地理学、工学、情報学、経済学等をベースにしながら、世の中の様々なデータを場所や位置という視点から整理し、使いやすく役に立つ「情報」に変えるための方法を研究しています。
空間情報解析研究部門
地形、水文、植生、社会、文化、言語、経済など多様な空間現象について、形状や分布などの空間的特徴を抽出する手法を開発し、背景にあるメカニズムを解明するための空間解析理論の構築と適用を行います。また、現象の将来予測や政策分析など、実社会の計画立案に資する空間意思決定支援システムも開発しています。

空間情報工学研究部門
実空間に置かれたセンサ群から生成される場所や時間に紐づいた莫大なデータや、インターネット上に散在する実空間の様相を反映したデータを効率良く取得するための諸技術、統合・マイニング手法の研究を行います。また、データの可視化、位置情報サービス、将来予測など、これらの時空間データに基づいた幅広い応用の研究を行います。

空間社会経済研究部門
時間と空間を切り口にさまざまな社会経済現象を分析し、社会経済問題の理解と解決を目指しています。分析は理論と実証の両面から行います。また、実証分析に必要となる時空間データの統計解析手法を開発します。さらにこれらと合わせ、全国の研究者が共用できる時空間データ基盤システムを整備することにより、都市・地域経済学を中心とする社会科学分野における実証研究の発展を促進していきます。

共同利用・共同研究部門
分散して存在する空間データや空間知識を空間情報基盤として再構築し、それらを連携させ高度利用する研究・教育支援環境を研究・開発しています。また、研究コミュニティの発展のためのイニシアティブの設計・実施・検証を行うとともに、空間情報基盤の社会的利用促進に必要となる環境・方法・制度の研究も行います。
イノベーション拠点の空間形成と評価 社会連携研究部門
本部門ではイノベーション拠点の形成を空間的な視点から研究しています。スタートアップ企業の立地動態およびインキュベーション施設におけるイノベーション促進施策の効果を、定量的・定性的に分析・評価して、新たなスタートアップ企業を誘引し、その成長を後押しする地域づくり・空間づくりのための知見を、実証的に明らかにします。

デジタル空間社会連携研究機構
デジタル空間社会連携研究機構ではIoTデバイスからのデータなどの多様でダイナミックなリアルタイム時空間ビッグデータを一元的に集約し、これらを統合した形で人々や企業の活動、交通・物流・商流から都市の拡大・環境変化、社会経済システムの変質・変動までを包含するデジタル社会空間をデータ基盤の上に構築すると共に学内関連分野の研究者を有機的に連携しつつ、データ駆動型の技術・サイエンスにより深化し、リアルタイム時空間データ解析・応用の新たな学理を構築します。同時に研究成果のデータ駆動型産業への展開と国際的な社会課題の解決支援につなげることを目指しています。詳細は こちら です。
グローバル空間データコモンズ社会展開 寄付研究部門
本部門では、まち全体のデジタルツイン化を行うとともに、各種地域課題のソリューション技術が民間等から出てくるように支援する事により、各地域のデジタルツインの社会展開・運営の自律化を促し、グローバルな空間データコモンズの形成を図ります。また、民間企業や地方自治体等のデータハンドリング・研修等を行い、人材育成を進めます。
シビックテック・デザイン学創成 寄付研究部門
デジタル空間社会連携研究機構と市民や地域企業といった多様なステークホルダーが関わることで、地域やコミュニティのためのデータ・デジタル活用を進めます。また、ソリューション開発過程に一貫して関わることができる学びや実践の場を各地に創成・展開します。多様性の豊かな対話と共創や多様な経験の機会を提供し、地域のデジタル力をボトムアップ的に底上げするような活動を育て・サポートしていく基盤を構築します。